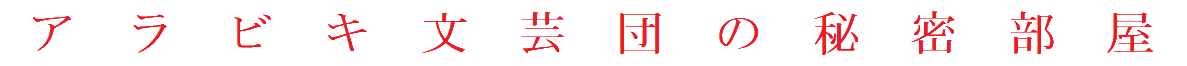
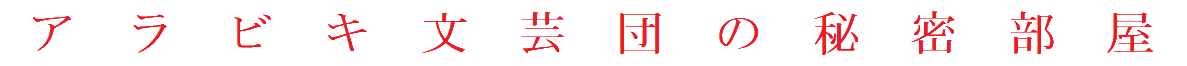
昔、『アラビキ団』というお笑いの深夜番組がありました。面白かった。しかし、こういう番組をゴールデンに持っていくと、アレヨアレヨと面白くなくなりますよね。同様に、マニアックな創作が、出版社で編集され万人向けに磨き込まれると、途端につまらなくなる。よくある話です。――当コーナーでは、磨き込まれる前の、まだアラビキ状態の原石を、ネットから探し出そうと試みます。
ボッ、ボッ、ボクラはアラビキ文芸団♪♪
よく、「読みたい本が無いから、自分で書いた。」と発言する新人作家がいますが、あれは粋がっているわけではない、本音だと思います。本屋の店頭に立つと、自分が八百屋にいるような錯覚に、時々囚われる事がある。並んでいる青物が、“青首大根”ばかりに見えてき、軽い目眩を覚えるのです。
勿論出版社の苦しい事情は分かる。彼等は趣味やボランティアで本を出している訳ではない、それで飯を食っている。マスがそれなりの数量を買ってくれる青首大根を出し続けねば、自分の首が絞まる。スーパーの青果部と同じで、地方の珍しい大根なんぞ、イベントの客寄せにしかならない。だが、そうやって青首ばかり出し続けた結果、急に首の絞まる事はないが、気付かぬ内真綿で首を絞め続けることとなった。
今の若い人の我慢強さにはほとほと感心させられます。青首ばかり食べ続けても、何の文句も言わない。まあ、生まれてこの方青首しか食べた事がないから、大根なんてこんなものだと思っているのでしょう。しかし年寄りはそれでは満足できない。昔の大根の味を知っていますから。薄味の青首にそっぽを向け、大根そのものを食べなくなる。それでも大根を食べたい年寄りは、古い産地や海外の変り種を探し回って、何とか口に入れたいものを見付けてくる。
しかし玉石混交の、それも石ばかりが目に付くネットの畑の中から、どうやって玉を見付けてきましょうか。まず考えられるのは、既成の公募文学賞の上位や最終候補作になりながら落選した作品を、ネットから拾い出してくる方法です。候補作や作者の記録から、ネットに検索を掛ければよい。比較的簡単に見付かるでしょう。ただしこれは、選別にいわば出版社のフンドシを借りた方法であり、しかも既に青首として選別され青首間での優劣で鼻の差で負けた玉を拾い上げることになってしまいます。勿論これらの作品も面白いでしょうし、ハズレは少ないでしょう。しかしそれなら、受賞作の方を金を出して読んでも、同じ事です。
本当のアラビキの、捩くれあがいた小説は、公募賞なら一次予選で落とされてしまうのではないか。そういう危惧、不安があります。一次予選では、まず邪魔なものを足切りして数を減らします。この時、日本語になっていないもの、小説になっていないものは勿論落とされますが、それ以外に、その賞のあるいは出版社の“毛色”に合っていないものも落とされるらしい(一次選考経験者の談によると)。この“毛色”の判断ですが、選考を依頼された者が、賞や出版社の意向(立場)をいわば“忖度”して決めているようです。となると、一次で落とされるものの殆どは日本語や小説としてレベルに到達していないものだとしても、それ以外にある程度の数“毛色違い”のものが落とされる。その中にこそ、“玉”の混ざっている可能性が極めて高い。しかしこの時点で世間から消えてしまうと、後に何の記録も残りませんから、ネットから探し出す事もほぼ不可能となる。(この理屈が正しいとすると、最悪なのは一次予選を通過するも二次予選で落ちた作品なのかもしれません。青首として認定されつつも、最初にふるいに掛けられる青首なわけですから。)
それでもめげずに、別の方法を考えてみましょう。まず考えられる方法は、レビューの追跡です。小説本体を読むのは大変です(読み終わって、あるいは読み始めてすぐ、ガッカリします)。ですがレビューならば読むのにさほどの手間は掛からない、指標として使えます。レビュー・ネットの中核ともいうべきネット小説のカリスマ・レビュアーが絡めばなおいい。これらを足掛かりにして、自分の好みに合った“毛色”の作品を探求していきます。こうしたレビューのし合い、評論のぶつかり合いが、隠れていた玉を浮き彫りにし発掘の端緒となります。(ただし、評論上の勝ち負けは、あまり参考になりません。その作品の良し悪しは、あなたにとっての良し悪しであり、決めるのはあなた自身なのですから。)
実際、万人にとってよい味のアラビキなどあり得ません。それでは青首になってしまう。アラビキであればあるほど、好む読者を逆に選ぶ。佐藤友哉さんの書かれた『1000の小説とバックベアード』に出てくる“小説にあらずして片説”という主張、キモに突き刺さります。多分小説というのは、共感を結ぶ道具としては、あまりに高尚過ぎるのでしょう。余りにユニークな所まで書けてしまうので、“片説”とならざるを得ないのです。
以前『バクマン』というアニメをテレビでやってました。結構面白かった、特に編集者とのやり取りが。ところが放映が終わってしばらくして、ハタと困った。主人公達が作り出した傑作とされるマンガの内容が、全然思い出せないのです。なのに、作中では駄作とされた、ミュージシャン・コージーの歌声で世界を変える話とか、アシスタント・モリヤ君の町が生きているという話とか、そういう独りよがりでダメダメとされた作品ばかりが印象に強く残り、かつまた読みたいと強烈に思う(対して、主人公達の描いた“傑作”には魅力を感じないようで、さっぱり読みたいと思わない。というかそれ以前にどんな作品だったかも思い出せない。少年漫画誌という設定だったから、仕方ないといえばそれまでなのですが)。
こういう独りよがりの作品にこそ、編集者の思惑に反して、強烈に読みたいと思わせる作品の核がある。“書きたい”も、“読みたい”も、前述の「読みたい本が無いから、自分で書いた。」という新人作家の言葉通り、同根のものです。ただどちらも徹底して独りよがりですから、両者の出会いは奇跡的なものにならざるを得ない(そんな奇跡に頼っていたら、出版社は飯の食い上げですからね)。だが、我々アマチュアには、そうした奇跡を辛抱強く待ち、時と金に飽かして探求し続ける権利とゆとりがある。
実際書く側からすると、小説は人のものを読むより、自分で書くことの方が断然面白いのです、徹底して自分の独りよがりを押し通せますから(これは、ゲームでも同じでしょう。ゲームは、人の作ったものをするより、自分の作ったものを人にやらせる方が、断然面白い)。ボルヘスが既に、『ハーバート・クエインの作品の検討』の中で、ハーバート・クエインの言葉として書いている。「文学が提供することのできるさまざまな楽しみのなかで、もっとも大きなものは創作である」「潜在的に、あるいは現実に、作家でない者はいない」「読者はすでに絶滅した種である」「すべての人間がその楽しみをえられるものではないから、多くの者はまがいもので満足しなければならないだろう」、と(岩波文庫『伝奇集』ボルヘス作鼓直訳)。
文芸に関わる者としての我々は、作者としても読者としても、個々の間が異星の知性体間ほども遠い。絶望的な距離で隔てられ、ファースト・コンタクトもままならない。ネットでマスメディアで、喧々諤々日々論争しているのに、実は声がまるで届いていない。同志とも呼べるようなマニアックな仲間の存在を想定しても、実はこれまた脳内の妄想の産物に過ぎない。結局、唯一の読者たる自分自身に向け、“具体物”として作品を書き続けるしかないのです。
で、それではそんな私の“毛色”は、片説漢振りはどのようなものかといえば、それは『SFにあらずんば、文学にあらず』に尽きます。SF以外の文学は、いわば文学の尻尾、単なるオマケに過ぎないと思っています。私の好むのは、『目玉焼きをひっくり返すような、丸ごとひっくり返す奇想』です。それを語り尽くすホラ話です。――以前ある文芸誌の編集長が「純文学の極みはドキュメンタリーだ」などとうそぶいていましたが、それとは真逆です。確かに“刺身文学”とも呼べるような、素材の味を丸ごと生かす文学もあり得ましょうが、それならむしろドキュメンタリーそのものを読みたい。せっかくフィクションを書くのに、フィクションでしか書けないものを書かずしてどうする、というのが私の趣向です。
それ故、本コーナーで取り上げられる作品も、私のそうした“毛色”のアンテナに引っ掛かったもの、ビンビンと来たもの、私の探求ルートの周辺に生息する作品ばかりとなりますので、ご了承ください(各人のルートは、各人で切り開いてこそです)。――閉塞した現代世界において、希望はSFの想像力にあり、と本気で考えております。基本的に人間にとって(いや、生物全般にとって)、“他者”とか“外界”とかは恐怖の対象です(その恐怖を和らげるために、ワクチンのように免疫を高めるのが“親の愛情”というものでしょう。そのワクチンを摂取されなかった個体が、いかに“他者・外界の恐怖”に過敏に反応するかは、想像に難くない)。そして神とは、人間を徹底的に相対化する、いわば“絶対他者・外界”的存在です。それはある意味、SFも同じです。すなわち今日、神に代わってSFはある。死んだ神(人格神)の機能を、“絶対他者・外界”たるSF(奇想)が引き継いだ。まさに継承者たる“神の子”ですな。(一般の文芸に較べ、SFの方がより“神性”が強い。前者が日常の卑近な人間しか相対化出来ないのに対し、後者は人間全般を相対化出来る。かつてピンチョンはSFを絵空事と呼びましたが、それは相対化を中途半端で終わらせる“想像力の貧弱さ”を露呈しているに過ぎません。喩えるなら、一本背負いがピシッと決まらず、途中で引っ掛かっている状態の文学です。その引っ掛かって止まっている様が滑稽で面白くて、人気があるんでしょう。逆にSFの絶対性を相対化している訳ですから。)